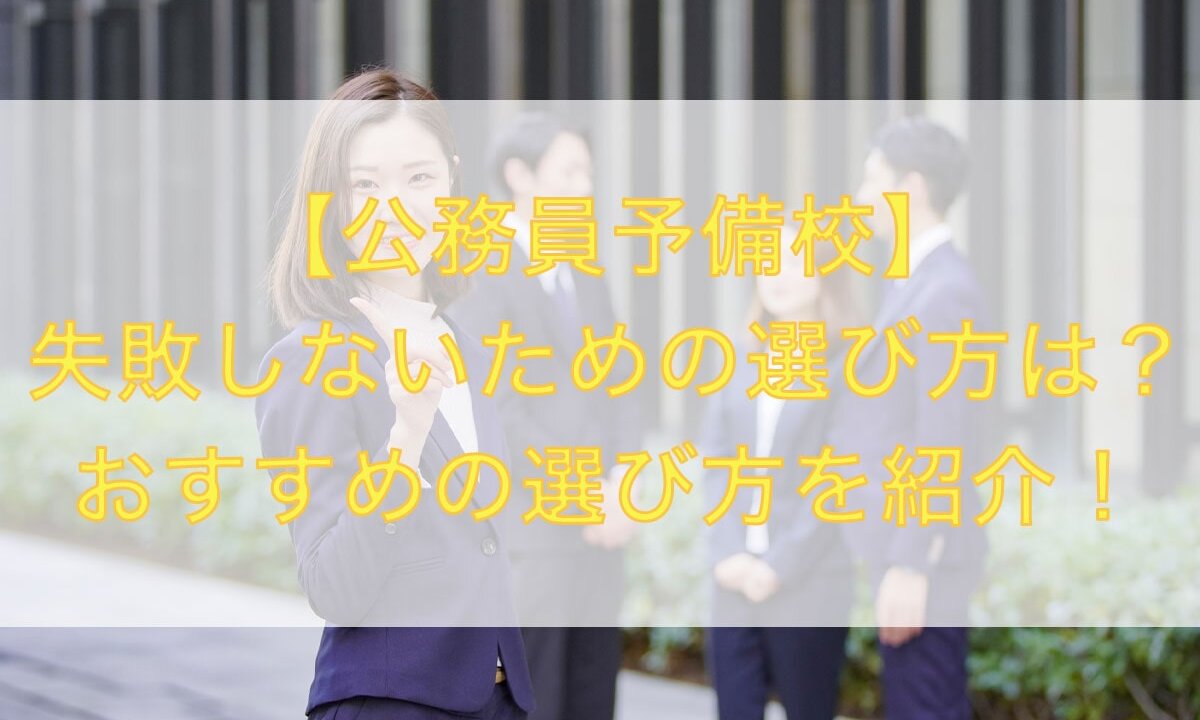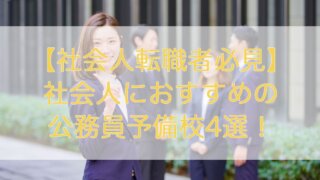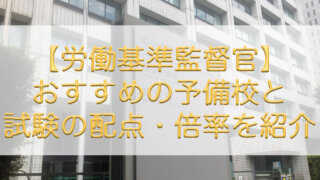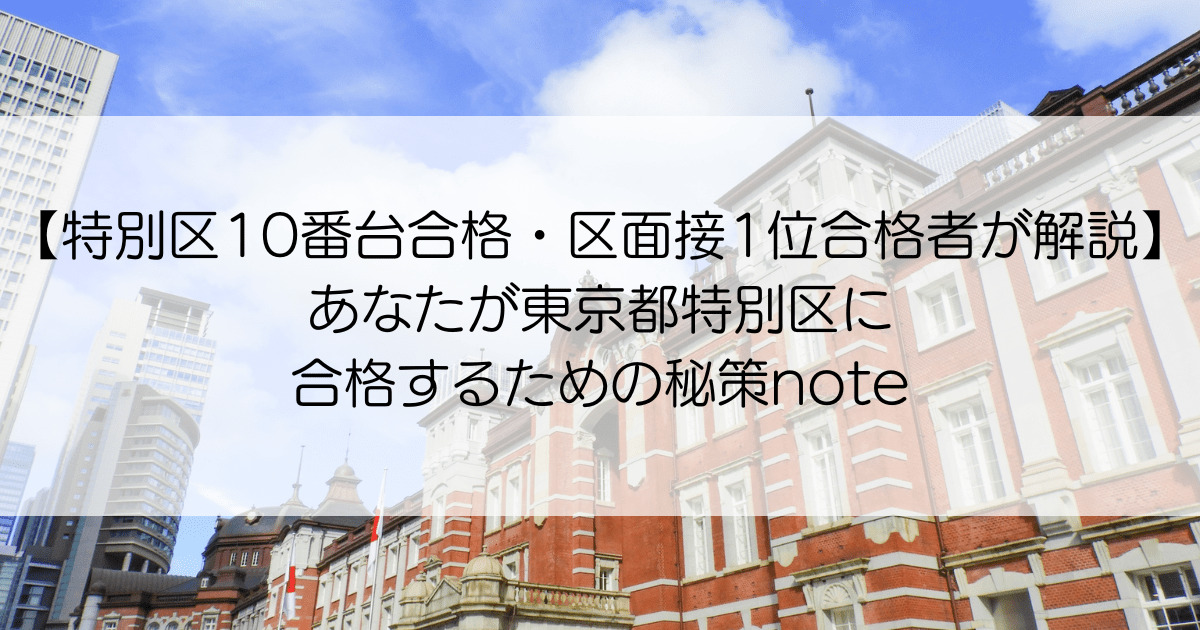種類が多くてよくわからない〜
こういった疑問にお応えします。
今回は、公務員予備校選びにおすすめの方法を私の実体験などを交えてご紹介します。
本記事の内容
- 公務員予備校選びに必要な4つのポイント
- 予備校選びで注意すべきポイント
- 試験に合格するためにもっとも重要なこと
【公務員予備校の選び方】そもそも公務員予備校に通うべき?→公務員予備校のメリットは大きい

そもそも公務員予備校って必要なのかな?
こういった疑問を持つ方もいるかと思いますが、公務員予備校に通うメリットは大きいです。
勉強の仕方や受験先の情報など、どれをとっても受験に有利な環境を得られるからです。
費用がかかってしまうのがデメリットですが、公務員になれば予備校費用はボーナス1回分できます。
ぼくが就職した役所でも95%が予備校出身者でした。
独学で合格した人は本当に少なかったです。
【結論】公務員予備校の選び方ポイント4点

公務員予備校を選ぶ上で大切な4つのポイントを解説します。
- 【重要】志望職種の合格実績の高い予備校を選ぶ
- 予備校に実際に足を運ぶ
- 費用の安い予備校を選ぶ
- 面接対策を受けられる予備校を選ぶ
順番に解説します。
ポイント1:【重要】志望職種の合格実績の高い予備校を選ぶ
| 職種 | おすすめ (※各予備校のリンクから資料請求できます) | 補足 |
|---|---|---|
| 国家総合職 | どの予備校も同じくらいの成果を上げている | |
| 外務専門職・防衛省専門職 |
| 合格者の9割がWセミナー |
| 心理職・福祉職・保育士 | 合格率は両校とも不明だが、面接対策まで受けられるクレアールに分がある | |
| 警察官・消防士 | 資格の大原が圧倒的に合格率が高い | |
| 都道府県庁・市区町村・国家一般職 | どの予備校も合格者多数 | |
| 理系技術職(土木・建築など) | LECの合格実績が圧倒的 | |
| 社会人採用 | いずれも合格率は不明だが、クレアールが社会人転職にもっとも力を入れている |
※上記で【おすすめ】と表記しているものは、合格実績が高くカリキュラムがしっかりした予備校です。
なりたい職種が決まっている人は上記のリンクから資料請求しましょう。(資料請求で割引が受けられるケースも多いです。)
公務員予備校選びで最大のポイントは、志望する職種の合格実績が高い予備校を選ぶことです。
公務員予備校は職種によって得意・不得意分野が存在するからです。
迷ったらとりあえず合格実績の高い予備校を選ぶのが安全です。
という方は、なりたい職種の予備校パンフレットをすべて請求して見比べるのがおすすめです。
ポイント2:面接対策が充実している予備校を選ぶ
面接対策を受けられるかどうかも非常に重要です。
公務員試験は筆記試験よりも面接試験の配点比率が年々高くなっているからです。
面接対策の指導を受けられる範囲に校舎があるのかなどを確認しましょう。
| 予備校名 | 模擬面接を受ける方法 | 校舎数 |
|---|---|---|
| TAC | 校舎のみ | 全国35校舎 |
| LEC | 校舎のみ (※県内にLEC校舎がない方のみWeb上での模擬面接が可能) | 全国52校舎 |
| 資格の大原 | 校舎のみ(全国109校) (※一部コースではオンライン面談も可能) | 全国109校舎 |
| EYE | 都内の渋谷・池袋・水道橋の3校舎のみ (※コース性はラインやメールで担任講師と面接相談可能) | 東京都内の渋谷・池袋・水道橋の3校舎のみ |
| クレアール | 水道橋本校のみで実施 (※ただし、予備校に通えない人はオンラインで面接指導を受けられる) | 東京都内の千代田区(水道橋)1校のみ |
| 伊藤塾 | 校舎のみ | 全国8校舎 |
②実際に公務員予備校に行ってみる
こういう方は必ず校舎を訪問して無料面談を行いましょう。
校舎を訪問することで以下のことがわかるからです。
- 予備校の学習環境は整っているか?(自習室の数・席数・利用者の民度)
- 担任講師やスタッフとの相性が良いか
- 自分に適した講義カリキュラムか?(※必ず事前にパンフレット請求を行うこと)
公務員予備校の受講は決して安くない買い物です。(最低でも20万円以上します。)
と後悔しないためには、必ず訪問しましょう。
補足:予備校見学に行くなら事前にパンフレットを読んで質問を考えておこう
校舎を訪問する際は必ずパンフレットを請求して質問内容を考えておきましょう。
面談の時間を無駄にしないためです。
と、時間を無駄にしないためにも、自分の疑問点や不安をできる限り明確にして面談に臨みましょう。
また、あらかじめパンフレットを読んでおくことで面談をより有意義なものにできます。
- パンフレットに載っているカリキュラムで実際にどんな教材を使うのか?
- パンフレットには合格者〇〇人と載っているが、自分の学校からどのくらい合格者が出ているのか?
【注目】小規模な予備校はパンフレットが充実している
クレアールとEYEは資料が充実しています。
これら2校の利用を考えている方にはおすすめです。
- クレアール⇨「社会人のための公務員転職ハンドブック」や「心理職志望者向けDVD」
- EYE⇨「予備校カリキュラム紹介のDVD」
これらのパンフレットやDVDなどを活用して予備校選びの参考にしましょう。
ポイント3:資料請求で予備校の雰囲気を掴む
予備校のパンフレットを読むことで予備校の雰囲気を知ることができます。
クレアール⇨社会人転職ハンドブック
資料請求でできる限り多くの割引情報をゲットする
資料請求などでできる限り多くの割引情報をゲットしましょう。
公務員予備校は最低でも20万円以上かかるため高額だからです。
パンフレット請求で割引クーポンを配布している予備校も多く存在します。
以下のリンクから、自分が志望する職種のパンフレットを請求できます。
【公務員予備校の選び方】通学制か?通信制か?

公務員予備校のカリキュラムには、①通学制と②通信制の2種類が存在します。
- 通学制:予備校の授業を校舎に通って受講する形態
- 通信制:予備校の授業をWeb上で受講する形態
どちらの学習形態を選択するかによって注意すべきポイントが異なります。
【公務員予備校選びの注意点】通学制を利用する場合
- 予備校の立地
- 自習室の環境
【通学制の注意点】予備校の立地
通学生を選択する上で際重要なのが予備校の立地です。
通学生の場合、授業を受けるために頻繁に通学する必要があるからです。
自宅や学校・会社の近くにあるか必ず確認しましょう。
遠ければ遠いほど通うのにコストがかかります。
【通学制の注意点】自習室の環境
自習室の環境にも注目しましょう。
通学生の場合ほとんどの時間を予備校の自習室で学習することになるからです。
自習室の席数が少なかったり、騒がしい場所だと思うように自習室を活用できないケースもあります。
【公務員予備校選びの注意点】通信制を利用する場合
- 面接指導のフォロー体制が整っているか
- 疑問点を気軽に質問できる制度が整っているか
【通信制の注意点】面接指導のフォロー体制
通信制の場合、最も注意すべきなのが面接指導の充実度です。
通信制の場合、面接試験対策などのフォロー体制が十分でないケースがあるからです。
校舎で面接指導を受けられない場合でも、メールやスカイプ(ズーム)などで面接指導をしてくれるのかどうかを確認しましょう。
万が一、予備校で面接指導を受けられない場合、他の面接手段がないか探してみましょう。(以下の記事が参考になります。)
【公務員予備校の選び方】公務員予備校選びの注意点

公務員予備校選びの注意点をいくつかご紹介します。
【公務員予備校選びの注意点】疑問点を気軽に質問できる制度が整っているか
疑問点を気軽に質問できる制度が整っているかも重要です。
通信制は近くに講師がいないため、疑問点をすぐに質問しにくい環境だからです。
勉強で壁にぶち当たった時に、電話やメールなどで疑問点を質問できるか詳しく確認しましょう。
今回紹介する予備校はいずれも電話やメールなどで質問できる制度が整っています。
【公務員予備校選びの注意点】アットホームな予備校か?ドライな予備校か?
予備校で継続して勉強し続けるためには、予備校の雰囲気も重要です。
EYEやクレアールなどの小規模な予備校は講師との距離が近く、親身に相談にのってくれる傾向があります。
EYEやクレアールなどの小規模予備校を考えている人は無料面談がおすすめです。
どっちが好みかは人によりますし、実際に校舎を訪れてみないとわからないことも多いので、入学前に校舎を訪れて受講相談を受けましょう。
【公務員予備校選びの注意点】比較に迷ったら直感で選ぶのも重要

最終的に比較に迷ったら直感で選びましょう!
比較に迷うということは、どの予備校もそこまで大差がないことを実感している証拠だからです。
どの予備校を選んだとしても最終的に合否を左右するのは本人の勉強量です。
なんとなくこの予備校の雰囲気が自分にあってるな〜
といった環境でコツコツと勉強できれば1年後には大きな結果となります。
そのため、自分がなんとなく居心地がいいといった直感も予備校を選択する上で重要な要素だといえます。
【補足】予備校選びで役立つおすすめのハンドブック(無料)
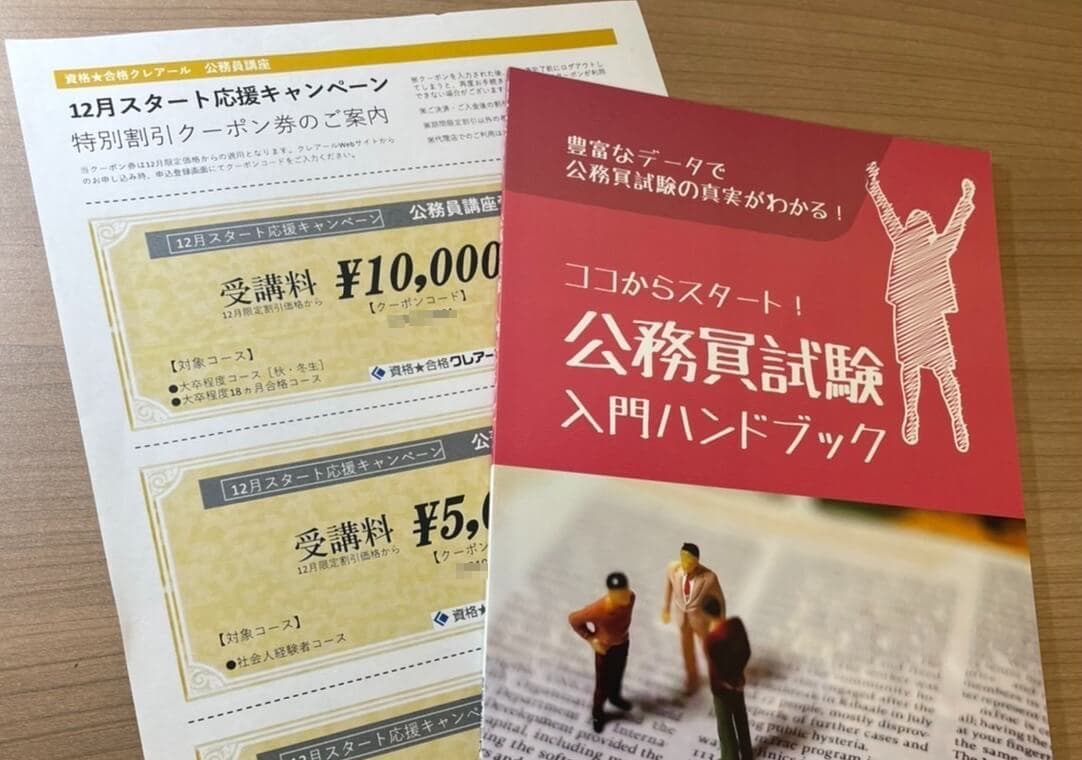
こんな口コミをたまに見かけることがあります。
このような失敗は事前の情報収集が足りなかったことが原因。
そんな情報収集不足を防ぐためには「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」がおすすめです。
- 【重要】合格者の体験記
→合格者が実際に勉強を行った手順を学べるため、合格する大まかなイメージをつかめる。 - 公務員の種類・職種について詳細が載っている
→職種や受験先を知ることで受験先の幅が広がり、予備校選びに役立つ - 受験先の自治体の倍率や年齢制限などの詳細データ
→受験先に合わせた細かな戦略を立てられる - 合格者が語る「私の苦労したこと&克服法」
→合格者の失敗談を知ることで、効率的な受験戦略を立てられる - 転職者のQ&A
→あなたの不安や疑問を解消できる
上記以外にも公務員受験に役立つ情報が満載。
書店で1,000円くらいで売っていてもおかしくないクオリティです。
公務員予備校を選ぶときだけでなく、志望先の選び方やその後の学習計画の参考にもなりますよ。
このハンドブックは公務員予備校のクレアールが発行している冊子ですが、他の予備校に通っている方でも無料で入手可能。
実際に、ぼくは何度も資料請求していますが、勧誘を受けたことは一度もありません。
\割引クーポンもついてくる/
※数量に限りがあります。
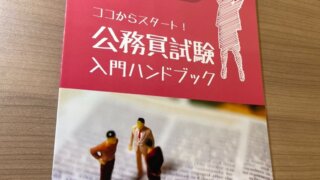
【まとめ】予備校選びは重要だけど最終的には自分の学習量がものをいう
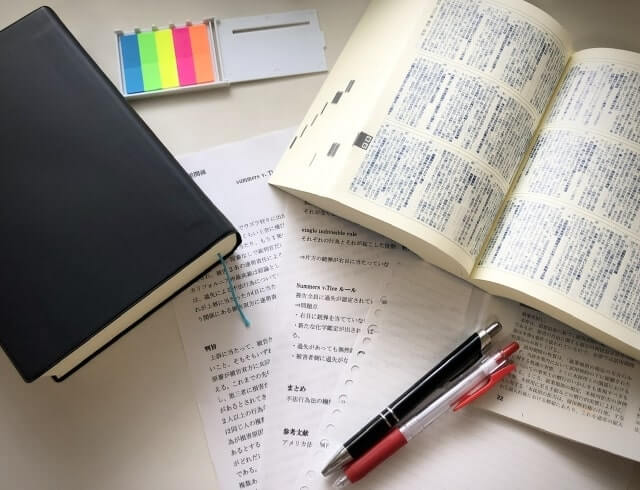
この記事で紹介した予備校選びを実践すれば、少なくとも
と大きく後悔することはまずありません。
そして、一度予備校を決めたらあとは与えられた環境でコツコツと勉強あるのみです。
予備校はあくまで勉強するための環境を作る場所です。
しかし、それよりも合否を決めるのはあなたがどれだけ勉強したかによります。
あなたの公務員予備校選びのお役に立てれば嬉しいです。
ここまでご覧いただきありがとうございました。