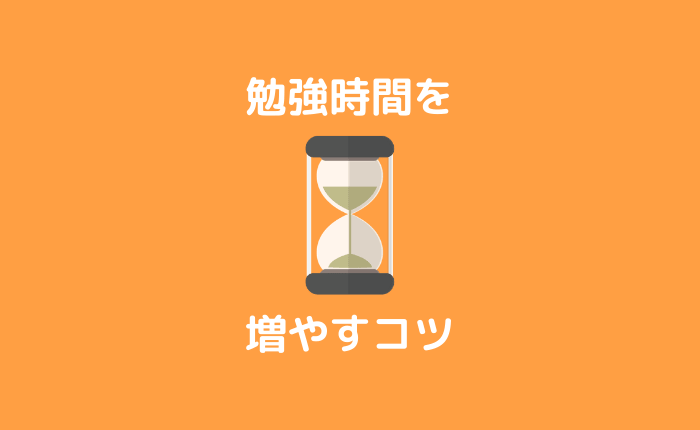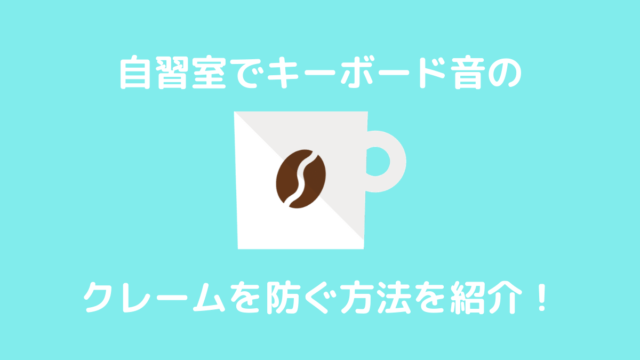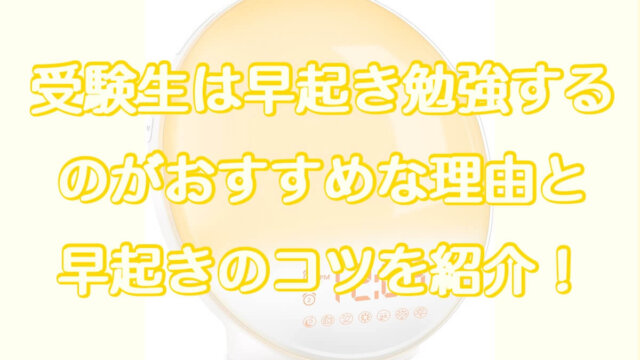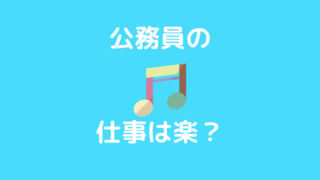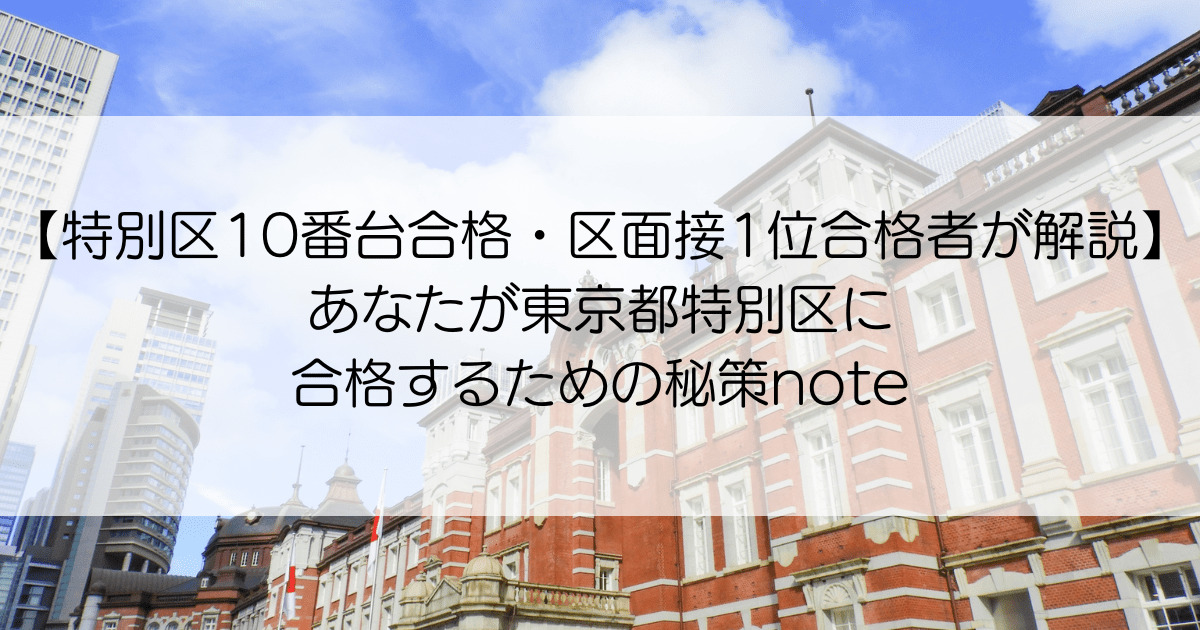現在勤めている市役所を1位合格した現役公務員のススムが、公務員試験合格に必要な勉強時間の戦略について解説します。
- 公務員合格に必要な勉強時間は1000時間〜1500時間
- 市役所の試験なら1500時間程度で1位合格が可能
- 合格に必要な公務員試験の勉強時間は大学生なら1000時間〜1500時間
- 社会人なら公務員試験の勉強時間は300時間〜500時間でも合格可能
- 【重要】公務員試験の合格者に共通している勉強時間の特徴
- 公務員試験の合格者は勉強時間が多い
- 早い時期から公務員の試験勉強に取り掛かっている
- 公務員試験の直前期ほど勉強時間が多い
- 市役所1位合格者の勉強時間(ススムの勉強スケジュール)
- 公務員試験の勉強時間を増やすコツ
- 【公務員試験】毎日決まった勉強場所で勉強して習慣化する【重要】
- 【公務員試験】勉強場所の決め方
- 【公務員試験】勉強時間のスケジュールの決め方
- 勉強以外の予定を極力排除する
- 1日の終わりにささやかな楽しみを用意する
- 公務員試験の勉強効率を挙げて勉強時間を有効に使う方法
- 【まとめ】公務員試験は勉強時間が合格を左右する試験
公務員合格に必要な勉強時間は1000時間〜1500時間
巷では公務員試験合格のために大体1,000時間〜1500時間程度必要と言われていますが、「ちょっと多いな〜」と感じるかもしれませんが、私の経験上、合格のためにもこのくらいの勉強時間が必要だと思います。
市役所の試験なら1500時間程度で1位合格が可能
私は市役所の試験で1位合格を取得した私は公務員試験で1500時間程度勉強しました。
私は公務員の受験勉強でStudy Plus(スタディプラス)というアプリを利用して勉強の記録をとっていたで、その記録をもとに勉強時間の内訳をざっくりと紹介します。
(ちなみに、スタディプラスは勉強時間の振り返りに活用できるので個人的にかなりおすすめです。)
ススムの公務員試験勉強時間の内訳教養論文:100時間
専門論文:100時間
専門記述憲法:25時間
専門記述政治学:25時間
専門記述行政学:10時間
専門記述社会学:10時間
専門記述公共政策:10時間
専門記述財政学:5時間
専門記述の演習:10時間
経営学:20時間
行政法:30時間
政治学:20時間
民法:50時間
ミクロ経済学:100時間
マクロ経済学:100時間
問題演習:100時間
財政学:20時間
数的処理:320時間
文章理解:50時間
社会科学:50時間
自然科学:70時間
人文科学:50時間
問題演習:10時間
時事対策:25時間
面接対策:150時間
教養試験のみの合計: 715時間
市役所レベルであれば巷で必要と言われている1500時間の勉強だけで十分に上位合格が可能だと思います。